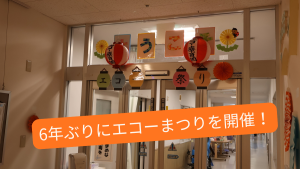家族に障害や病気を抱える子どもがいる場合、そのきょうだいとして育つ子どもは「きょうだい児」と呼ばれます。きょうだい児は、幼いころから家庭内で特別な役割や我慢を求められることが多く、孤独感や不安、葛藤を抱えることも少なくありません。しかし、その存在や心のケアについては、まだ社会的に十分に理解されているとはいえないのが現状です。
そのなかで、家族が一時的に介護や看護の手を離し、心身を休める「レスパイトケア」は、きょうだい児の健やかな成長を支えるうえでも欠かせない取り組みです。親が心に余裕を持てることで、きょうだい児一人ひとりに目を向けた関わりが生まれ、子ども自身も安心感や自己肯定感を育みやすくなります。
本記事では、きょうだい児とはどのような立場の子どもを指すのかをはじめ、成長の過程で直面しやすい悩み、そして家庭や社会ができる支援やケアの方法について解説します。きょうだい児への理解を深めるための参考となれば幸いです。
きょうだい児とは

きょうだい児とは、障害や重い病気をもつ子どもの兄弟姉妹を指す言葉です。一般的に「兄弟」や「姉妹」と表記されることが多い中で、あえて「きょうだい」とひらがなで表す理由は、兄・弟・姉・妹といった立場の違いを超えて、すべての子どもを等しく含めるためです。
成人したきょうだい児については、「きょうだい者」と呼ぶこともあります。
療育や医療の場で注目される背景
療育や医療の現場では、これまで障害や病気をもつ子ども本人への支援に焦点が当たりやすい傾向がありました。しかし近年、その子どもを支えるきょうだい児の存在も見過ごせない大切なテーマとして注目されています。
きょうだい児は、家族の一員として日常的にサポートの役割を担うことがあり、時に孤独感や責任感、自己犠牲を抱えることもあります。こうした現状を受けて、医療・福祉の分野では「きょうだい支援」の必要性が広がりつつあります。
きょうだい児とヤングケアラー

ヤングケアラーとは、障害・病気・精神疾患などを抱える家族の世話や介護、感情面の支援などを担う18歳未満の子どもを指します。きょうだい児の中には、家庭内で兄弟姉妹の介助や家事、保護者のサポートなどを日常的に担っているケースも少なくありません。このような役割を担う子どもたちは、ヤングケアラーとしての側面を持ち合わせている可能性が高いといえるでしょう。
きょうだい児がヤングケアラーになる背景には、「家族として当然に助けるべきだ」という価値観や、外部の支援が行き届かない環境が影響しています。そのため、本人が「ケアをしている」という意識を持たないまま、無理を重ねていることも多く見受けられます。
きょうだい児が抱える悩み
きょうだい児の悩みは、幼少期から思春期、そして大人になる過程で変化していきます。年齢や環境によって抱える不安や葛藤は異なるため、それぞれの段階でどのような課題が生じやすいのかを理解しておくことが大切です。
ここでは、きょうだい児が抱える悩みを成長過程にあわせて解説します。
幼少期
幼少期のきょうだい児は、親の関心が兄弟姉妹にばかり向いていると、自分が後回しにされていると感じてしまいやすい傾向です。「遊んでほしいのに親が来てくれない」「自分の話を聞いてもらえない」などの思いが蓄積していくと、孤独感や寂しさにつながりやすくなります。
また、障害や病気について十分に理解できない年齢であるため、「なぜ自分の家庭だけ違うんだろう」と、戸惑いや不安を抱くこともあります。
学齢期
小学生から中学生にかけての時期には、友人関係や学校生活の中で悩みが表面化しやすくなります。たとえば、兄弟姉妹の特性を理由に周囲からからかわれたり、偏見にさらされたりすることがあります。
また、親から「手伝ってほしい」と頼まれる機会が増え、自分の勉強や遊びの時間が制限されるケースもあるでしょう。その結果、「自分は我慢しなければならない」という意識が強まり、ストレスや不満を言い出せないまま抱え込むことにつながります。
青年期
高校生から大学生にかけての青年期は、進学や進路選択といった人生の大きな節目に直面する時期です。本来ならば自由に選択できる場面でも、「家を離れてはいけないのではないか」「親を助けるために地元に残るべきではないか」と考えることがあり、選択の幅を狭めてしまうことがあります。
また、同世代の友人との違いを意識してしまい、自分だけが損をしているように感じることも少なくありません。
成人期
成人後は、親の高齢化や介護の問題が現実的な課題となります。きょうだい児は「親が亡くなった後、兄弟姉妹の生活をどう支えるか」という不安を抱きやすく、結婚や就職、居住地の選択に影響を及ぼすこともあるでしょう。
また、自分自身の生活と家族への責任の間で葛藤しやすく、心理的な負担が続く場合もあります。
きょうだい児が抱えている問題

きょうだい児は、家庭や社会の状況によってさまざまな問題に直面します。周囲から理解されにくいことも多く、心身への影響や日常生活の制約につながる場合もあります。
ここでは、その代表的な問題について整理し、具体的に見ていきましょう。
周囲から偏見の目で見られる
きょうだい児は、学校や地域社会において周囲から偏見や誤解を受けがちです。障害や病気をもつ兄弟姉妹に対して十分な理解が得られていない場合、「変わった家庭」「特別な事情のある家族」として扱われたり、からかいの対象になってしまうケースがあります。
また「きょうだいなのだから理解できるはず」「しっかり支えて当然」といった周囲の無意識な期待も偏見の一種です。本人にとっては大きな負担であり、「もっと頑張らなければならない」というプレッシャーにつながります。
精神的な負担がある
きょうだい児は、日常生活の中で強い精神的負担を抱えることがあります。兄弟姉妹の療育や医療的ケアに多くの時間や注意が必要とされる家庭環境では、自分の思いや欲求を後回しにせざるを得ない状況が生じやすくなるでしょう。その結果、「自分は我慢しなければならない」「親に迷惑をかけてはいけない」という意識が強まり、気持ちを素直に表現できなくなる可能性があります。
また、幼少期から家庭内でサポート役を担うことで、年齢に見合わない責任感やプレッシャーを感じることも少なくありません。自由に遊ぶ時間や安心して甘える体験が制限されることで、ストレスや不安を心に溜め込みやすくなります。
将来の選択肢が狭まる
きょうだい児は、進学や就職といった人生の節目において、家族の状況を考慮して将来の道を制限してしまうケースがあります。
たとえば「親を助けるために遠方の大学には進学できない」「将来的に兄弟姉妹の生活を支える必要があるから地元で就職する」といった判断をすることが考えられるでしょう。本来であれば自由に選べるはずの進路や生活の選択肢が、家庭の事情によって狭められてしまうことがあります。
また、「自分の夢を追いかけてよいのか」「兄弟姉妹を置いて自分だけ幸せになっていいのか」という迷いや罪悪感を抱くこともあるため、選択に伴う心理的負担は小さくありません。
人間関係に影響が出る
きょうだい児は、家庭の状況が人間関係に影響を及ぼす可能性があります。兄弟姉妹の障害や病気について周囲の理解が得られない場合、からかわれたり誤解されたりすることで、友人関係に距離が生まれることがあるでしょう。
また、家庭での役割や責任を優先するために、友人と過ごす時間を制限せざるを得ないこともあります。将来に目を向けてみれば、恋愛や結婚を考える際に「家族を支えられるかどうか」が判断基準となり、関係の継続や選択に影響を与えてしまう可能性もあります。
きょうだい児に対するケアの方法

きょうだい児が安心して成長していくためには、周囲の大人が適切なケアを行うことが欠かせません。
ここでは、具体的にどのようなケアの方法があるのかを見ていきましょう。
一対一の時間を意識してつくる
きょうだい児にとって、親と一対一で過ごす時間は「自分も大切にされている」という実感につながります。障害や病気をもつ兄弟姉妹に時間が多く割かれる中で、たとえ短い時間でも「今日は二人でおやつを食べよう」「一緒に買い物に行こう」といった特別な機会をつくるとよいでしょう。
そうした時間は、子どもの心に安心感を与え、孤独感を和らげます。ポイントは、時間の長さよりも「自分だけに向けられた時間」であることです。きょうだい児の気持ちを満たす小さな積み重ねが、健やかな心の成長につながります。
気持ちを受け止め共感する
きょうだい児は、寂しさや嫉妬、怒りなどマイナスの感情を抱えることがあります。しかし多くの場合、「こんな気持ちを持ってはいけない」と心にしまい込みがちです。親が「そう感じるのは自然なことだよ」「あなたの気持ちをわかっているよ」と言葉にして受け止めるだけで、子どもは安心し、感情を素直に表現できるようになります。
きょうだい児は家庭の中で「手伝って当たり前」と受け止められやすいため、自分の努力や存在が見過ごされることがあります。そのため、「ありがとう」「助かったよ」といった感謝の言葉を意識的に伝えることが欠かせません。
レスパイトケアの活用もおすすめ

きょうだい児との時間を確保するためは、レスパイトケアの活用がおすすめです。レスパイトケアとは、障害や病気をもつ子どものケアを一時的に専門機関や施設が担うことで、家族が休息やリフレッシュの時間を確保できる仕組みを指します。保護者が心身を休められるだけでなく、その間にきょうだい児とゆっくり向き合う時間を持つことができる点が大きなメリットです。
また、レスパイトケアを通してきょうだい児は「自分も大切にされている」という実感を得やすくなります。親子で一緒に遊んだり、安心して話を聞いてもらったりする時間は、自己肯定感を育み、心の安定にもつながります。家庭だけで抱え込まず、地域の制度や支援サービスを積極的に取り入れることで、きょうだい児にとっても家族にとってもより良い環境を整えられるでしょう。
仙台エコー医療療育センターでは、医療と福祉の両面を備えた体制のもと、安心して利用できるレスパイトケアを医療型短期入所を通して提供しています。詳細が気になる方は、仙台エコー医療療育センターの「療育連携科」にぜひご相談ください。
きょうだい児へのサポートを提供している団体
国内には、きょうだい児への理解と支援を広げるために活動している団体が様々あります。ここでは、代表的な団体やその活動内容について紹介します。
きょうだい支援を広める会
「きょうだい支援を広める会」は、きょうだい児が抱える不安や孤独感に寄り添い、社会全体にきょうだい支援の必要性を発信している団体です。講演会や研修の実施、情報発信などを通して、きょうだい児とその家族、さらには教育・医療・福祉の関係者に対して支援の重要性を伝えています。
特に、きょうだい児の声を社会に届けることを重視しており、学校や地域における理解の促進にも取り組んでいます。
Sibkoto(シブコト)
「Sibkoto(シブコト)」は、きょうだい児やその家族が体験や思いを共有できるオンラインプラットフォームです。コラムやインタビュー、当事者の体験談などが掲載され、情報を得られると同時に「自分と同じ立場の人がいる」という安心感を得られる場となっています。
また、きょうだい児や家族が孤立しないようにするため、オンラインで誰もがアクセスできる仕組みを整えている点が特徴です。地域の枠を超えてつながることができるため、支援の輪を広げる役割を果たしています。
まとめ|きょうだい児への理解と支援を広げよう

きょうだい児が抱える孤独感や葛藤は、家庭の中だけでは十分に解消されないこともあります。そのため、周囲の大人や社会が「あなたは一人じゃない」と伝えることが大切です。
同じ立場の仲間がいることを知らせたり、地域や学校に安心して相談できる場があることを示したりするだけでも、子どもの心は大きく救われます。きょうだい児にとって必要なのは、特別な支援だけでなく「理解してくれる人がいる」という確かな実感なのではないでしょうか。
重症心身障害のある子どもやきょうだい児、家族を支えるために、仙台エコー医療療育センターでは、医療と福祉の両面からサポートを行い、一人でも多くのご家族が安心して暮らせる環境づくりに取り組んでいます。
当センターの療育連携科では、日々の介護や看護から離れて心身を休めるレスパイトケアにもつながる短期入所の相談や調整を行い、ご家庭の負担を軽減するお手伝いをしています。家族が安心して休息をとれる時間を確保することは、きょうだい児への丁寧な関わりにもつながり、子どもたちの心の安定を支える大切な一歩となります。
こうした活動は、皆さまからのご寄付によって支えられています。寄付は単発・毎月からお選びいただけ、決済は外部サイト「Syncable」で安全に行えます。
あなたの思いが、確かな支援となって届きます。ぜひ応援をお願いいたします。
寄付で応援する