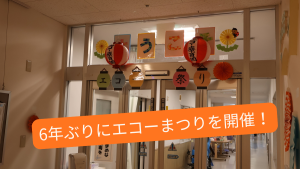小児医療を受けている子どもが成長していく中で避けて通れないのが「移行期医療」です。これは、小児診療科のみならず、成長にともない生じる「成人のからだ」に対処するために成人診療科にも治療の場を引き継ぐまたは一部を担ってもらう過程を指します。
厚生労働省からの通知では、安心して新しい成人診療科へ移行または併診できるよう、十分な説明と連携が求められます。ところが現実には、十分な説明がなされないまま移行を勧められる。または、移行先の医療機関を保護者が探すなど、多くの家族が移行期医療の難しさに直面しています。
近年、宮城県内でも移行期医療についての相談が増えていますが、その実態の一部を明らかにするために仙台エコー医療療育センターが独自に調査を実施しました。
調査概要
・対象:仙台エコー医療療育センター短期入所・生活介護・外来を利用している重症心身障害児者・医療的ケア児者、光明支援学校に通う重症心身障害児者・医療的ケア児者
・対象年齢:15~40歳
・調査方法:調査用紙、Google Formを利用したアンケート形式
・調査期間:2025/4/1~6/30
〈症例〉
・男性:39例(26.2±6.6歳)
・女性:31例(26.8±6.7歳)
〈医療的ケア〉
・栄養、呼吸:23例
・栄養:12例
・栄養、呼吸、排泄:7例
・排泄:6例
・栄養、排泄:1例
・呼吸:1例
・なし:16例
・無記載:4例
調査対象となった70人のうち、多くが日常生活を支えるために欠かせない医療的ケアを受けていました。具体的には「栄養管理と呼吸管理が必要」という人が23例と最も多く、次いで「栄養のみ」が12例、「排泄管理のみ」が6例、「栄養・呼吸・排泄のすべてが必要」という人も7例いました。また、人工呼吸器を装着している人は17名にのぼりました。
一方で、まったく医療的ケアを必要としない人も16例存在しました。
ここで注目すべきは、「栄養」や「呼吸」といった生命維持に直結するケアを必要とする人が大半を占めているという点です。胃瘻ボタンやチューブをもちいた栄養補給、人工呼吸器による呼吸補助は、24時間体制での支援が欠かせません。こうした医療的ケアを継続的に受けられるかどうかが、移行期医療における課題の一つといえます。
調査結果
移行の進捗状況
調査では、移行期医療がどこまで進んでいるのかを尋ねました。その結果、人によって状況が大きく分かれていることが明らかになりました。回答割合は、下記のとおりです。
| 移行の現状 | 症例数 | % |
| すでに移行期医療が完了している | 22 | 31.4 |
| 移行している途中で順調に進んでいる | 7 | 10.0 |
| 移行している途中で難航している | 18 | 25.7 |
| 移行の話は出ていない | 13 | 18.6 |
| 主治医から移行せず小児診療科で診療を継続すると明言されている | 7 | 10.0 |
| 主治医から移行するように言われているが応じていない | 2 | 2.9 |
| 主治医以外から移行するように言われているが、応じていない | 1 | 1.4 |
| 合計 | 70 |
この数字から見えてくるのは、41.4%が移行を完了または順調に進めている一方で、44.3%は「難航している」か「そもそも話が出ていない」という現実です。その背景には「受け入れ先が見つからない」「主治医からの説明が不十分」といった問題が潜んでいると考えられます。
移行期医療に関する説明の有無
移行期医療において重要なのは、家族が「なぜ移行が必要なのか」「どのような選択肢があるのか」を理解し、納得したうえで進められることです。しかし、今回の調査ではそのプロセスに大きなギャップがあることが浮き彫りになりました。移行期医療についての説明に対する回答割合は、下記のとおりです。
| 医師からの移行期医療についての説明(複数回答) | 延べ回答数 | % |
| 移行期医療の3つの類型についての説明があった。 | 3 | 4.8 |
| 成人診療科への移行についてのみ説明された。3つの類型については説明がなかった。 | 27 | 43.5 |
| 説明がなく、年齢を理由に「卒業」もしくは「今後は診療できない」と告げられた。 | 22 | 35.5 |
| 医師からの説明はなかったため、別の医療機関の医師に相談した。 | 6 | 9.7 |
| 医師からの説明はなかったため、成人移行支援センターに相談した。 | 1 | 1.6 |
| 外来主治医と病棟主治医で、異なる説明を受けた。 | 2 | 3.2 |
| その他:自由記載 | 1 | 1.6 |
| 合計 | 62 |
調査結果によると、医師から「移行期医療の3つの類型」(厚生労働省が提示しているモデル)についてきちんと説明を受けた人は、わずか3例(4.8%)にとどまりました。
一方で、「成人診療科への移行についてのみ説明があった」「説明がなく、年齢を理由に『卒業』『今後は診られない』と告げられた」「説明がなかったため、別の医療機関や移行支援センターに相談した」との回答が90.3%にも及んでおり、十分な説明を受けられないまま移行を迫られている事実がわかりました。
移行先の提示方法
小児科から成人診療科への移行にあたって、医師がどのように移行先を示したのかを尋ねたところ、結果は大きく分かれました。
| 移行先の医療機関と成人診療科がどのように提示されたか | 症例数 | % |
| 小児診療科の医師から移行先医療機関を紹介されたが、移行先の成人診療科の医師との連絡は診療情報提供書のみであった。 | 22 | 44.9 |
| 小児診療科の主治医から移行先医療機関を紹介された。診療情報提供書の他に、移行先の成人診療科の医師と主治医との話し合いが行われていた。 | 8 | 16.3 |
| 小児診療科の主治医からは、移行先医療機関・診療科の紹介や提示はなく、保護者が自分で探すことになった。 | 14 | 28.6 |
| 小児診療科の主治医からは、移行先医療機関・診療科の紹介や提示はなく、他の医療機関などに相談した。 | 3 | 6.1 |
| 成人移行支援センターから移行先の医療機関と成人診療科を紹介された。 | 1 | 2.0 |
| その他 | 1 | 2.0 |
| 合計 | 49 |
最も多いのは「小児診療科の医師から紹介を受けたが、成人診療科の医師との連携は医療情報提供書のみ」で、全体の44.9%を占めています。つまり、形式的には移行の紹介があるものの、実際の医師同士のコミュニケーションは十分に行われていないケースが目立つといえます。
また、28.6%は「紹介や提示がなく、保護者が自分で探すことになった」ケースです。これは移行支援体制が不十分であり、家族に大きな情報収集・調整の負担がかかっている現状を示しています。
小児診療科の主治医から成人診療科の医師と直接の話し合いを伴って紹介された例は16.3%にとどまりました。
実際の受け入れ状況
移行先で実際に受診したときの受け入れ可否については、次のような結果でした。
| 移行先の成人診療科を受診した際の受け入れ状況 | 症例数 | % |
| 受診して、快く受け入れてくれた | 26 | 55.3 |
| 受診して、なんとか受け入れてもらった。 | 14 | 29.8 |
| 受診する前の問い合わせの段階で断られた。 | 6 | 12.8 |
| 受診したが、診察の結果で受け入れ不可と言われた。 | 1 | 2.1 |
| 合計 | 47 |
半数以上は安心して受け入れられたものの、14.9%は受診前後で拒否されていたことになります。断られた理由としては、下記が挙げられます。
| 断られた理由 | 延べ回答数 |
| 重症心身障害の診療経験がないため | 6 |
| 患者さん本人が、意思表示をできないため | 2 |
| 基礎疾患について診療経験がないため | 2 |
| ADL(日常生活動作)レベルが低いため | 1 |
| 医療ケアに対応できないため | 2 |
| 基礎疾患が、治癒する疾患ではないため | 1 |
| 体格が小さいため | 1 |
| 合計 | 15 |
入院治療
体調が急変したとき、すぐに入院治療を受けられるかどうかは命に直結します。しかし調査の結果、重症心身障害児者・医療的ケア児者とその家族にとって、入院は決して当たり前に保障されたものではないことが明らかになりました。
| 現在、入院加療が必要になった時の状況(複数回答可) | 症例数 | % |
| 体調不良時に入院治療できる医療機関がない。 | 26 | 25.5 |
| 入院が必要な時に、受け入れ先を探すことが非常に困難である。 | 26 | 25.5 |
| 入院できると言われている小児診療科でも、なかなか入院させてもらえず困ったことがある。 | 12 | 11.8 |
| 入院を断られ自宅で経過をみるしかなく症状が悪化したことがある。 | 5 | 4.9 |
| 外科的な治療を断られたことがある。 | 2 | 2.0 |
| 体調不良時に入院治療できる小児診療科がある。 | 20 | 19.6 |
| 体調不良時に入院治療できる成人診療科がある。 | 11 | 10.8 |
| 合計 | 102 |
回答を複数選択できる形式で尋ねたところ、「体調不良時に入院できる医療機関がない」と答えた人は26例(25.5%)、同じく「入院が必要な時に受け入れ先を探すのが非常に困難」と答えた人も26例(25.5%)にのぼりました。また、「入院できるとされている小児診療科でも実際には入院させてもらえなかった」と答えた人が12例(11.8%)いました。
さらに深刻なのは、「入院を断られ、自宅で経過をみるしかなく、その結果症状が悪化したことがある」という人が5例(4.9%)いたことです。また、外科的治療を断られたケースも2例(2.0%)ありました。
「看取り」に関する説明
移行期医療をめぐる調査の中で、特に重く受け止める必要があるのが「看取り」に関する説明です。今回の調査では、70例のうち11例(平均年齢27.7歳)が、医療機関から『今後は積極的な治療は行わない』『看取りを考えてほしい』と説明を受けていました。
| 医療機関において年齢、ADLレベルの低さ、基礎疾患を理由に「今後は積極的な治療をしない」または「看取り」の説明を受けたことがありますか。 | 症例数 | 平均年齢 |
| はい | 11 | 27.7 |
| いいえ | 59 | 26.2 |
まとめ|考察と課題
今回の調査は、宮城県内の重症心身障害児者における移行期医療の現状を具体的な数字として示す、貴重なものとなりました。
今回の調査から、移行期医療はおよそ半数が「完了」「順調」あるいは「小児診療科での継続」により、大きな問題なく進んでいると評価できます。しかし、「完了」と「順調」と回答した群の移行先医療機関をみると、重症心身障害児者施設と訪問診療所が多いことが分かります。これは、仙台エコー医療療育センターを利用している重症心身障害児者を対象として調査を行ったためのバイアスと考えられるでしょう。
一方で、移行に関する説明は十分とは言えません。35.5%は説明なく年齢を理由に「卒業」もしくは「今後は診療できない」と告げられたと回答しており、移行のみを説明された43.5%と合わせて約80%が、きちんとした説明のないまま小児診療科の診療を打ち切られたこととなります。
また、移行先医療機関の提示についても大きな課題があります。「小児期発症慢性疾患を有する患者の成人移行支援を推進するための提言(日本小児科学会雑誌127巻1号61~78 2023年)」の主要項目の転科支援の項には、
「転科先が見つかったから」と紹介状を持たせて、単に成人診療科へ転科させることは行うべきでない。転科支援を行いながら転科を進める必要がある。双方の診療科が患者の病状について十分に連携した上で、患者・保護者に
1)転科する成人診療科に関して十分な説明をし、
2)小児診療と成人診療の違いを説明し、
3)不安をできるだけ取り除いて納得を得た後、
転科することが重要である。もし、転科後の病状悪化などが考えられるときは無理な転科をするべきでない。
と記載されています。しかし、44.9%は紹介状(診療情報提供書)のみの移行であり、28.6%は提示すらなく、保護者が自ら移行先医療機関を探すことになっています。
入院治療の現状については、複数回答であるため示す比率は全回答数を母数としていますが、入院治療ができない・困難であるとの回答が69.7%を占めています。移行先が一般入院病床を有しない重症心身障害児者施設や訪問診療所である場合には、入院治療が困難となっていることが一因になっていると推測されます。
総じて、今回の調査は移行期医療における説明不足、医療機関間の連携不足、入院治療体制の脆弱さといった課題を示しています。今後は、制度面の整備に加えて、医師間の協力を強化し、保護者の負担を軽減する取り組みが求められます。